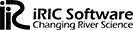
土石流シミュレーションの条件設定において、
タイムステップだけを変えただけで、解析結果(土石流の氾濫範囲)が大きく異なります。
(タイムステップ以外の地理的・計算条件はすべて同じです)
添付ファイル①は、タイムステップを0.001,ファイル②はタイムステップ0.002です。(DepthMax)
氾濫の範囲(幅)は、100m以上違ってきます。
Morphoのシミュレーションでは、すべて同じ条件で実行しても、結果がことなることはありましたが、タイムステップの違いはかなり大きいです。
粗度係数・流動深・粒径等の条件以上に、タイムステップの設定が最も結果を左右するものでしょうか。
コメント
非常にわかりやすい例をご紹介頂き,ありがとうございます.
もう少し詳しく調べなければ分かりませんが,おそらく,0.001秒の計算結果はある程度上手く計算できており,0.002秒の計算はタイムステップが大きすぎて上手く計算できていないと判断できます.
土石流は,対象地点の勾配が平衡勾配以上であれば,地盤が浸食されて土石流の規模が大きくなります.そのため,タイムステップが大きすぎると,計算誤差で本来土石流が流れないような解析格子に土石流が流れてしまい,その場所の勾配が平衡勾配以上であれば,地盤が浸食されて土石流が発達してしまいます.0.002秒ではそのような現象が発生していると予想されます.この点は土石流の数値シミュレーション独特の難しさです.洪水氾濫などであれば,計算誤差で本来流れない場所に水が流れてもそこで水の量が増えることはありませんが,土石流の場合は計算誤差で流れ込んだ地点の勾配が平衡勾配以上であれば体積が増えることがあり,土石流が発達しない場所でも発達してしまうことがあるので注意が必要です.
なお,粗度係数や流動深はMorpho2DHによる土石流解析の設定条件ではありませんので,何か誤解されていると思いますよ.
ご返信ありがとうございます。
1)平衡勾配の値はいくつでしょうか。もしくは、どのようにして決まるのか、教えて頂けますか。できれば、自分で設定できると助かります。
デフォルトでは、緩い渓床勾配でも侵食されてしまい土石流が堆積(停止)していきません。
2)タイムステップですが、0.002は大きすぎで、0.001の方が適切となると、正直、PCの計算時間が長くなりすぎて辛いですね。マニュアルでは0.01とありましたが、これでは全然大きすぎるということですね。
3)マッピングに粗度があったため、入力していましたが、関係ないのですか(河床の粗度係数を思って入力していました)。では、渓床の状態はプログラムには関係ないということですか。例えば、林内の方が粗度が大きくながれにくいなど。
4)流動深ですが、マニュアルには最小流動深の設定がありますが、これも関係ないのでしょうか。
またお時間があるときにご返信頂けますか。