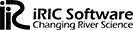
お世話になっております。
とある河川でNays1D+を用いて、不等流計算を行っています。
対象とする河川の粗度係数は、基本的に0.03にしていますが、一部の区間(5.2~5.6)でコンクリート三面張りになっており、そこだけ0.025としています。
粗度係数を全て0.03にした場合と、粗度係数を小さくした場合の一部の区間(5.2~5.6)の結果を比較すると、粗度係数を小さくした方が水位が高くなりました。
逆に、粗度係数を0.03より大きくすると、0.03の時と比較して水位が下がることもあります。
基本的に粗度係数を小さくすると水位が下がり、粗度係数を大きくすると水位が上がると感じているため、計算結果が誤っているような気がしています。
このような計算の挙動を解決したいのですが、どなたかに助言をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
※横断測量データの座標は実際の座標と異なります。(フォーラム投稿用に意図的にずらしています)
コメント
minagawa様
水理学という学問における知識で,以下のようなものがあります.
(ご存知だったらごめんなさい)
①連続式
Qを流量,Vを流速,Aを河川の断面の面積とすると,以下の式が成り立ちます.
Q=V×A
②開水路におけるマニングの平均流速公式
Vを流速,nをマニングの粗度係数,Rを径深,iを河床勾配とすると,以下のような式が成り立ちます.
V=(1/n)×(R^(2/3))×(i^ (1/2) )
径深Rは水深hと近似可能なので,
V=(1/n)×(h^(2/3))×(i^ (1/2) )
と書き換えることができます.
今回,解析ではマニングの粗度係数を変化させていますね.
つまり,nの値を変化させているわけです.
流量Qや河川の形状(断面など)は変えていない前提で話を進めます.
式①より,流量Qと断面積Aは変わらないので,流速Vは一定とすると,
式②でマニングの粗度係数nだけを仮に大きくした場合,流速Vは一定なので,
水深hが大きくなります.
なので,ここまではminagawaさんの理解は正しいです.
ただし,式①の断面積Aは,川幅B,水深をhとすると,河川の断面が長方形だと近似すると,
A=B×h
となります.
つまり,流速が式②の影響で水深hが大きくなると,式①の断面積Aも大きくなります.
流量に関しては一定なので,その場合,今度は流速Vを小さくする必要があります.
流速に関しては式②に移ります.
今度は,粗度係数nは設定された値なので,式②で変動可能なパラメータはhしかありません.
そのため,水深hが下がります.
水深hが下がると,断面積Aは小さくなります.
すると今度は,式①より,流速Vを大きくしなければなりません.
流速Vに関して,式②で合わせにいくと...(以下,循環するので省略)
このように,水深や流速を繰り返し計算することで,真値に近づけていく,という計算が解析内で行われています.
実際にはおそらくこの2つの式以外にもいくつかの水理公式が関係しています.
詳しくはiRICのソルバーマニュアルを確認すると,実際にどのようなモデルにどのような水理式が考慮されているのか,分かると思います.
なので,理論的には一般的に粗度係数が大きくなると水深が上がり,粗度係数が小さくなると水深も下がるはずですが,
解析結果が必ずそのようになるとは言えないかもしれません.
yuto様
ご回答ありがとうございます。
ご回答を要約すると、ケースバイケースであるとおっしゃっているのだと認識しています。
ただ、粗度係数を大きくすると水位が下がり、粗度係数を小さくすると水位が上昇するような結果は、ケースバイケースだけでは正直納得し難いです。(水理学的に正しい挙動なのか、計算の設定が誤っているのか、モデルの不具合なのか判別ができない)
どのようなメカニズム・現象でもって、このような結果が出ているのか、可能であればお教え頂ければ幸いです。